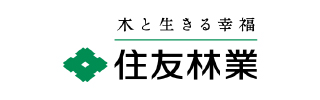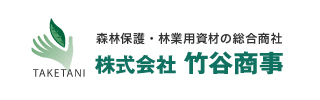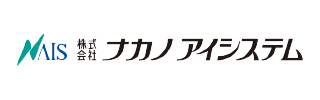日時:2001年12月3日(月) 10:00 ~ 16:30
会場:岐阜県県民ふれあい会館 3F 大会議室
岐阜県森林GIS運用状況と今後の取り組み
岐阜県農山村整備政策課農山村情報係長 水谷 嘉宏
岐阜県においては、平成9年度に「岐阜県GIS導入研究会」「同技術部会」を設立し、平成12年度までに「導入指針」「データ整備・更新指針」「空間データ発注仕様書」「岐阜県域統合型GIS基本設計書」を取りまとめてきた。導入指針の中で唱われたGISセンターについては、本年11月に(財)建設研修センター内に「ふるさと地理情報センター」が設立され、共用空間データの県民等へ公開に向けた体制が整いつつある。
県の森林GISは、これらの作業に先行するかたちで、主として森林簿・森林計画図の更新・作成を目的に開発を行い平成10年10月より運用を開始したが、運用開始後も以下の機能等の追加を行っている。
- 図面データのDXFファイル出力
- 流木災害監視地域判定のための処理
50mメッシュデータの整備、地質データの整備
判定テーブルの作成 - 森林のゾーニング判定用テーブルの作成
- 山地災害危険地データの整備
- 高分解能衛星(イコノス)画像データの活用
このほか、一部の地域であるが森林計画図(等高線等)のベクター化を試みた。
当県の森林GISは、現状では森林GISと称するより森林計画GISと表現したほうが適当であり、対象業務が比較的限られていると認識している。そのため、業務原課からの新たな要求に対しては個別の対応が必要となっている。
当面の課題についても、
- ふるさと地図情報センターとのデータ受け渡し
(G-XMLもしくはShapeファイルへの変換・取り込み) - 詳細な高さデータの取得と利用
(森林基本図のベクター化と小流域・渓流線・傾斜などの判定) - 農地(農業振興地域)のGISデータとの相互利用
(県の組織再編に伴い、森林GISと農地GISの管理を当係が行うため。) - 現地機関等へのGISデータの利用業務の展開
があげられる。
なお、森林GIS以外の業務も含めて、森林関係の現行の情報処理業務は「森林プロジェクト」として再開発に着手されており、これらにより、本来の森林GISに進化していくと期待している。
システムの開発時には総合的で多機能なものを求めがちであるが、処理するためのデータ(情報)の整備と更新が最重要であることを維持管理に携わる中で痛感している。
三重県森林GISについて
三重県環境部森林保全課森林管理グループ 山田 長生
三重県では、平成12年度より一部モデル地域で、県独自の森林ゾーニングを実施し、森林を環境林と生産林に区分しました。平成13年度は、その結果にもとづき、県下一円の森林ゾーニングを実施しています。
そのためには、森林に関する様々な情報を数値化し、地図化することが求められます。それを実現するための手段として、平成9年度より森林GISの開発に取り組みました。平成11年度には、全県分の森林基本図、森林計画図、空中写真、森林簿の入力を実施して基本システムを整備し、平成12年度にはサブシステムとして治山・林道・保安林・林地開発・県行造林の森林行政情報、そして、そのほかに環境行政情報として、水道水源、廃棄物処理場位置、温泉泉源、アメダス、国土利用計画図、土地利用規制図、植生図等のデータ整備を進めました。
また、一人一台パソコンの普及により、職員一人ずつに一台のパソコンが割り当てられており、森林GISを利用したい職員が、使える環境を整備することから、WebGIといった形態のGISを運用しています。
森林GISの運用には、データの更新が必要不可欠であり、それは情報の発生源で行うことが、作業の効率化を図ることができ、精度を落とさずして集約できるとの考え方から、できるだけ職員が自前でできるシステム及び体制作りを構築しています。
県で作成したデータは、市町村・森林組合に、無償で提供しています。近年、市町村・森林組合でも、GISの有用性が認識されつつあり、今後は、森林簿等の精度を高めるためにも、関係団体からのデータのフィードバックがスムーズにできる体制作りを構築する必要があります。
また、本年ユO月から、森林GISで整備したデータの一部を、インターネットを利用して、県民の皆様に広く情報公開しました。三重県では、さらに情報公開を進めて、適正な森林管理を進めていきます。
(三重県森林GISのアドレス http://www.forest-gis.pref.miw.jp/)
森林GIS開発の現状と今後の展開
株式会社キャディックス IT事業本部 横山 猶吉
弊社は、これまで新潟県、熊本県、島根県、岐阜県及び長崎県(敬称略:導入順)向け森林情報システム(森林GIS)の開発に携わってきた経験から、森林GISを次のようにとらえている。
Ⅰ.森林情報システムとは
森林情報システムとは、単なるコンピュータシステムではない
↓
コンピュータシステムを活用した森林業務の運用全般の仕組み
- 森林が有している様々な機能を高度に発揮させる
- 持続可能な森林経営を推進する
- 多様な森林作りをする
コンピュータシステムの為のシステム構築から森林業務遂行の為のコンピュータを活用した管理運用の為の仕組み構築
☆ポイント
- 初期データ整備
- コンピュータシステムで扱う情報を安価で正確に、かつ迅速に電子化しなければ、コンピュータシステムはただの箱に過ぎない。
- データ更新
- 業務遂行とシステムの融合
- 精度の向上
- 森林情報システムを正しく運用
- 利・活用
- 新たに必要となる情報の管理運用と施策への活用
Ⅱ.森林情報システムも成長
森林業務は長期に亘る:システム運用のライフサイクルも長い
業務遂行者やコンピュータハードウエア/ソフトウエアを同一環境(同一構成)で永続させる事は非現実的 → 改変時における最適資源の導入
森林情報システムも時間と共に成長(樹木と同じ)
- システムの利活用がなされ業務展開が広がって行く
- 森林業務は長期に亘るので、業務の遂行手順・方法が変化して行く
- システムの環境も日進月歩で変化して行く
↓
経験を生かした森林情報システムの運用保守とコンサルタントが重要
Ⅲ.今後のGISの方向性
オープン・ソフトウエアアーキテクチャ
+
専門分野におけるシステム構築技術/サービス(コンサルタント)
森林組合における森林GIS
松阪飯南森林組合森林保全課長 杉本 美春
三重県においては、平成9年度より森林GISを導入され、基本システム、森林資源情報管理システムの開発に取り組まれています。
県庁の取り組みに対応するため、平成13年4月に広域合併した当組合においても、県内の森林組合に先駆け県庁と共同歩調をとりながら、合併前の松阪市森林組合では平成11年度に、森林組合みえ中央では平成12年度にそれぞれ市単、町単で基本システ及び各種機器を導入し、現在はそのシステムを活用して過去の施業履歴等を三重県と連絡を取りながら入力作業中の段階です。
当森林組合の現在における取り組みとしては、事業別・年度別ファイルに綴じて保管してある、過去数十年にわたる施業履歴等山林調査資料をコンピューター上で一括管理をしながら今後の事業に即対応できるようにすることと、森林基本図・森林計画図・空中写真を同一画面上で確認する事により、GPS機能を取り入れて治山の保育事業等で活用していきたいと思います。
三重県で来年度から導入される森林環境創造事業においても、地域の協議会等でこの森林GISを活用してゾーニング作業を進めていきたいと思っています。
また、各施業地についてGPSを利用した座標管理をすることにより、世代交代により所有山林の所在がわからなくなった場合の現地確認と、森林計画図上での位置の確認及び訂正をどのように行っていくかが今後の課題になっています。
以上の事を考慮しながら、県・市町村・森林組合がより効率的な活用がで鼓るよう、今後の森林簿等のデータ更新をどのような方法で三重県としていくかを早急に確立したいと思います。
また、各種施業を円滑に進めるために、森林所有者との日常のやり取りの中で、職員のだれでもが簡単に利用できる森林GISシステムを早く確立したいと思います。
森林GISに対する現場からの提言
白鳥町森林組合 参事 笠野 和幸
- 導入の経緯
-
要望(希望)
- 森林組合がもつ膨大な森林情報の有効に活用を模索
- 現況と森林簿等台帳との情報の整合性を図り実体に即した管理台帳の必要性
- 既存の各種システムの連動性図り、森林情報の一元的管理の必要性
導入方針- 基本図や航空写真と台帳の照合が簡易に行えること
- 情報の検索等が簡易に行えること
- 既存のシステムからの移行がスムーズに行えること
→ 新たな GISをコアとしたシステムを開発
ペーパシステムからデジタルシステムへ
- システムの概要
-
- 地理情報システム(基幹システム)
森林簿検索、施業図検索、現場写真の登録(小班毎に30枚登録可能) - 測量図作成システム
現地調査で得られた森林境界等測量情報をGISに直ちに反映させる - 造林補助金申請システム
森林施業の履歴として、自動的に森林簿(GISの)に反映させる
以上の3システムを統合している。
- 地理情報システム(基幹システム)
- 組合での利用事例
-
- 森林所有者検索 組合員サービス(山林管理指導、事業確保)
- 間伐対象林分検索 間伐推進(事業の推進、事業計画・管理、山林整備推進)
- 現況写真のデータベース化 受託林の施工管理
- 測量データのデータベース化 境界の明確化
- 明らかになった問題点
-
- システムの問題点 ①検索項目の検討②操作性の問題③システムの連動性
- データの問題点 ①森林簿所有者の相違 ②林班ポリゴンの問題 ③林小班界の相違
- 今後への提言
-
- 県のシステムとの連携を図りデータの共通化により精度の高い森林簿を樹立
- 森林の現況を明確に把握するため森林簿・森林計画図・実測図・現況写真の一元化
- 森林施業計画と事業実績(履歴)のリンクによる現場施業に基づいた計画樹立支援
- 将来の事業拡大
- 森林施業の営業はもとより、今後GISとGPSを組み合わせる事により山林の地籍測量調査への事業拡大も行って行きたいと考えている。